
概要
築城名人(マニア)・加藤清正が心血を注いで築城した巨大な城塞です。高い石垣とおびただしい数の櫓群、幾重にも折れ曲がった通路を張り巡らせた実戦型の要塞で、テレビ番組などでもしばしば「最強の城」として紹介されています。
もともとは室町時代に肥後国守護の菊池氏一族が熊本の地に築かせた千葉城が始まりでした。その後、同地に「隈本城」が築かれました。戦国時代においては、肥後国は豊後国主で九州北半分を勢力下においていた大友宗麟の支配下となり、家臣の城氏が居城しました。その後、羽柴秀吉の九州征伐で城氏は撤退し、秀吉に臣従した佐々成政に与えられます。佐々成政は秀吉の命を破って領内で検地を実施したことにより、肥後国人一揆を引き起こしてしまい、その責任を取らされて切腹となります。後任として秀吉子飼いの武将で築城名人といわれた加藤清正が肥後北半国19万5,000石の領主となって入城しました。
その後清正は千葉城・隈本城のあった茶臼山丘陵一帯に巨大な城郭を築きはじめ、清正が関ケ原の戦いで東軍に与した功で肥後一国52万石に一躍出世したことで、隈本城を現在の「熊本城」に改めます。しかしながら清正の子・加藤忠広が改易となり、加藤氏の熊本統治はわずか2代で幕を閉じます。その後小倉藩より細川氏が入城しましたが、細川氏の代でも城の拡張が続けられ、最終的に櫓の数は62を数えました。
幕末の西南戦争では、政府軍が重要拠点とし、西郷隆盛が率いる反乱軍の標的となりましたが、反乱軍は熊本城の武者返しに苦戦し、結局一兵たりとも城内に侵入することができませんでした。このとき西郷隆盛は、「おいどんは官軍に負けたとじゃなか。清正公に負けたとでごわす」との有名なセリフを残しています。
明治時代においては、陸軍第6師団司令部が置かれ、第二次大戦中は米軍の激しい空襲を受けますが奇跡的に焼失を免れました。
戦後には天守閣が鉄骨コンクリート造りで復元され、2007年には本丸御殿も復元されますが、2011年に発生した熊本地震で、全石垣約7万9000平方メートルのうち、約三割の約2万3600平方メートルに崩落・膨らみ・緩みが発生するなど甚大な被害を受けました。2022年現在、復元に掛かる総工費は354億円で完全復旧は2052年度という気の遠くなる時間が掛かる見通しとなっています。
見どころ
加藤清正が築いた西国一の難攻不落のお城で、当時はおびただしい数の櫓と石垣で守られていて、震災前までは多くの櫓や石垣を見ることができましたが、震災後は観覧ルートも限定されているほか、多くの櫓が解体となってしまっていたり、石垣も崩落してしまっているのが少し残念です。
でも震災後の今でも天守と天守を囲む石垣群は圧巻の一言です。ぜひ完全復旧後(2052年!)に再来したいお城です。
写真&散策記
大分に赴任してから早3年、なかなか熊本市内には来ませんでしたが、ようやくやって来ました!
熊本の商店街でラーメンを食してから向かいます。
市街地からも立派な天守閣がみえてきます。

お城に着くとまずは鉄壁の熊本城を作った築城マニアの加藤清正公がお出迎えです。

ついでに城址碑もパシャリ。

2016年に発生した熊本震災の爪痕は想像以上で7年たった今でも至る所で修復作業が進められています。

順路に沿って行幸坂を登っていきます。
戦前に明治天皇が熊本城を訪れたときに、当時熊本城の登城路が急坂だったため、急遽陸軍がこの緩やかな坂を造成したことから「行幸坂」と呼ばれています。

戦国ファンイタ車仕様のタクシーを発見しました。
(戦国武将ではなくガラシャのところが・・・)

行幸坂の右手に飯田丸五階櫓が見えてきますが、残念ながら櫓は震災影響で解体となっているようで、石垣は修復中のようです。手前が備前堀という飯田丸の堀跡になります。


震災当時はわずか一列の石垣が櫓を支えていたことら「奇跡の一本石垣」と呼ばれ、熊本県民を大いに勇気づけたといわれています。

当時奉行所が置かれていた「奉行丸」の石垣です。
震災でえぐれた箇所が痛々しいです・・・

石垣は崩落防止のためかワイヤーと金網で固定されています。

券売所で入場券を買って城内へ。ここからはスロープのようなものを渡っていきます。
当時能や茶会が行われていた「数寄屋丸二階御広間」が見えてきます。ここも石垣が崩れて地面がむき出しになっています。

間の石垣がちょうど崩落してしまっていて数寄屋丸の建物も危なそうです。

数寄屋丸の崩落した石垣の隙間から天守閣(左側)と本丸御殿(右側)が見えてきます。

本丸御殿の立派な石垣。攻め上るのは困難を極めそうです。

本丸御殿の石垣は「二様の石垣」と呼ばれていて、古い石垣(右側)に新しい石垣(左側)が継ぎ足されていてできたとても珍しい造りになっています。

スロープはこんな感じになっています。
本当は地面の上を石垣の高さを味わいながら散策したいですが、いまだ危険が多いということでしょうね・・・

手前が本丸御殿大広間、奥が数寄屋丸です。

本丸御殿は二つの石垣を跨ぐように建っているため、下を通る通路があります。
真昼でも暗いことから「闇り通路」と呼ばれています。
全国的にもとても珍しい地下通路で、幸いにも震災では目立った被害がありませんでした。

闇り通路を抜けるといよいよ天守閣です!

と、その前に本丸お休み処で土産物を見ます。
熊本城天守閣の形をしたペットボトルがおもしろくてつい買ってしまいました。

天守閣のベンチのプレートでこんなのを発見しました。
熊本支店長の名前が熊本って・・・

いよいよ城内へ!

城内はものものしく補強がされています。

外部から見える天守閣の石垣はあとで築き足された石垣とのことで、城内で築城当時(1599年)の石垣を見ることができます。

1階と小天守をつないでいた石階段です。

城ファンとしてはあまり見たくない城内エレベーターですが、おもいやりエレベーターなので仕方ありません。

秀吉が加藤清正に宛てた肥後国を与える書状です。
「お前はよく頑張ったし、秀吉の役に立ちそうだから肥後国を与える。熊本城に在城するように」と書かれているとのことです。戦国時代も転勤族ですね。

「天守軸組模型」です。
昭和の熊本城再建にあたり制作され、この模型を参考に設計することで熊本城の正確な復元ができているとのことです。

こちらは天守上段模型。
天守閣最上階の「御上段の間」をミニチュアで再現したものになっています。

加藤清正もこんな感じで優雅に過ごしたのでしょうか。

昔(明治?昭和?)に撮影された熊本城の写真が展示されています。
絶対に攻め落とせなさそうですね。
できればこの時代の熊本城を散策してみたかった。

天守最上階は展望室になっています。
外に出られないのが残念。

天守最上階から見下ろす風景。

震災後の熊本城を支える「摩擦ダンパー」
大地震が来たときは透明の箱の中に入っているプレートが動いて免震する仕組みになっています。

城内の観覧を終了して天守閣を後にします。
豪華さはないですが、無骨で堅実なお城です。

天守裏手の建物や石垣も崩壊の跡が痛々しい。

天守裏手の虎口と思われる場所。通行禁止になっています。

「横手五郎の首掛石」です。怪力で知られた武将・横手五郎が築城の際に首に掛けて運んだと呼ばれる石です。ちなみに横手五郎は75人力あったそうです。

天守の裏手から。

熊本城内で唯一当時の姿を保っている「宇土櫓」です。
3重5階地下1階のつくりで天守に匹敵する規模と構造のため、「第三の天守」と呼ばれます。


虎口を抜けて南大手門に向かいます。

南大手門の方面から。左が宇土櫓で右が天守閣です。

南大手門は倒壊防止の処置がとられています。この後、解体されるとのことです。

南大手門を抜けて西大手門へ。西大手門は既に解体された後のようです。

西大手門の外から。奉行丸の石垣です。かなり崩落してしまっています。
奥に見えるのが未申櫓です。


熊本城本丸防御の最前線の曲輪である「西出丸」です。
こちらも崩落した石垣がそのままになっています。

最期に奉行丸の未申櫓を眺めながら最初の行幸坂に戻ります。

以上で散策終了です!
とても見ごたえのあるお城でしたが、ぜひ復旧後にまた見に来たいです。
あと30年後か・・・


公式パンフレット




城データ
- 城名 熊本城(銀杏城)<日本百名城No.92>
- 種別 平山城
- 登城日 2023年2月11日(土)
- 住所 熊本県熊本市中央区本丸1−1
- 電話番号 096-223-5011
- スタンプ設置場所 桜馬場城彩苑
- 公式HP 熊本城公式HP
- 入場料 大人800円
- 駐車場 有料・2時間まで200円以降1時間ごとに100円
- 所要時間の目安 2時間30分程度
- 混雑度 大
- 注意点 特になし
※管理人が登城時の情報です。登城の際は必ず公式HPで最新情報をチェックして下さい。
管理人の勝手な評価
~城として~
- 難攻不落度 ★★★★★(現代でも落とせなさそう・・・)
- 歴史に浸れる度 ★★★☆☆(本来は浸れるのですが震災がなければもっと・・・)
- 他では見れない度 ★★★★☆(西日本一の難攻不落の城をご堪能ください)
- 総合評価 ★★★★☆
~行楽地として~
- アクセス性 ★★★★☆(九州新幹線熊本駅から近いです)
- 登城のしやすさ度 ★★★★★(スリッパでも全く問題ないです)
- 分かりやすさ度 ★★★★★(解説など充実しています)
- 景観度 ★★★☆☆(天守より熊本市街を一望)
- 女性と行ける度 ★★★★☆(くまもんとかとセットで訪れましょう)
- 総合評価 ★★★★☆
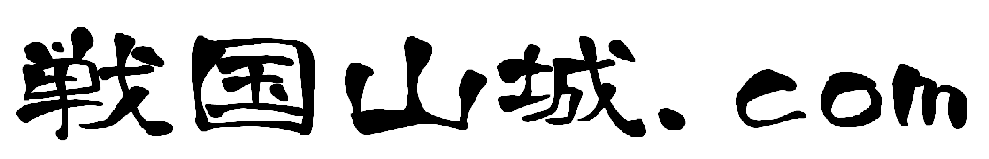



コメント