
■概要
備中国の戦国大名・三村元親が本城とした城で、貴重な現存12天守の一つであります。
仁治元年(1240年)、秋庭三郎重信が備中有漢郷(現・岡山県高梁市有漢町)の地頭に任ぜられて臥牛山の大松山に砦を築いたのが発端となり、その後時代の流れとともに、現在の備中松山城が建つ小松山に縄張りが拡張され、やがて三村氏が治める城となります。
戦国時代、三村家当主・元親は毛利氏を後ろ盾に備前の戦国大名・宇喜多直家と対立しますが、元亀元年(1570年)備中に攻め込んだ直家を迎え討つために出陣したところ、直家と通じた元親の部下の裏切りにより一時城を奪われることとなります。元親は城を奪還し、大松山・小松山を含めて多くの砦を築き、臥牛山一帯を要塞化します。
<戦国時代の中国地方東部の勢力図>
三村氏は毛利氏と宇喜多氏に挟まれています(左下の方)
(引用元:播磨屋さんのサイト「戦国武将家紋地図」より)
その後、毛利氏が小早川隆景の進言により宇喜多氏と事実上の同盟を結ぶこととなったため、天正2年(1574年)元親はついに毛利氏と離反して、畿内を統一して中国方面への進出を目論んでいた織田信長と結ぶこととなります。
これを知った毛利輝元は8万の軍勢を出して備中松山城を除く備中国の支城を次々と落とし、松山城を孤立させます。最終的には松山城も小早川隆景によって落とされ、元親は自害します。(備中兵乱)
その後は毛利氏の領有となりますが、毛利氏含む西軍が関ヶ原の戦いで敗れて後、幕府が城番として小堀正次・政一を置き、政庁としては山城は不便な時代となっていたことから、麓に御根小屋が築かれました。
その後、幕末までに池田氏、水谷氏、安藤氏、石川氏、板倉氏が入城しますが、明治の廃城令によって商家にわずか7円(5万円)で売却されることとなります。明治の廃城令では全国の城が破却されましたが、あまりにも不便な場所にあったため幸運にも破却を免れます。その後城は荒廃が進みますが、昭和初期に地元の小学校教諭によって修復が呼びかけられ、高梁町によって修復の予算が組まれることとなります。
その時の修復事業では、高梁町の各小学校の児童が一人一つの瓦をもって山頂に運びました。
また、2016年の大河ドラマ「真田丸」ではオープニングで備中松山城の映像が使われます。
(真田家は信州・上州の大名であるためストーリーとは無関係です)
■見どころ
天守閣は二層二階で現存12天守の中では最小ですが、最も高い位置に立っている現存天守です。
現存天守かつ山城であり、戦国ファンであれば満足すること間違いなしです。
通常の中世の山城には白壁の建物は存在しないため、標高400mを超える山の頂上に漆喰の白壁の天守があるというだけでロマンがあります。天守は小ぶりであるものの大手門をはじめとした高石垣は圧巻です。
自然と人工が融合した素晴らしい山城で、備中兵乱の歴史に思いを馳せましょう。
<備中松山城大手門跡の高石垣:天然の岩と石垣が一体化しています>
■写真&散策記
高梁市街から山に入り、城見橋公園駐車場というところで車を停めます。
ここからシャトルバスもありますが、折角天気も良いので、城まちステーションで弁当を買って歩いて登ることにします。
ふいご峠駐車場(シャトルバスの終点)からは山道に入っていきます。
大手門に向けてどんどん登っていきます。
太鼓を叩く櫓跡ですが、麓から太鼓櫓を中継して城内に情報を伝達する仕組みでした。
ここからは城まちステーションでもらったマップ(城山ウォーキングマップ)が見やすいです。
大手門跡です。
天然の岩盤とも一体化しています。
大手門だけで興奮してだいぶたくさん写真を撮りました!
漆喰の白壁「土塀」が見えてきます。
大手門は大河ドラマ「真田丸」のオープニングでも使われていました。
真田丸では城内に水が流れているという設定でした。
少し戻って「犬走」。
細い通路が搦手(城の裏手)まで通じていたと言われています。
二の平櫓跡です。平櫓は一重の屋根しか持たない櫓で、西国に多かったと言われています。
白壁の土塀と石垣がずっと向こうまで続いていきます。
ここの土塀は現存のもので、鉄砲狭間と矢狭間の両方が設けられていて、敵を射撃できるようになっています。
上番所跡です。足軽番所より上役の人が詰める場所だったのでしょう。
大手門から遥か上に見上げた土塀たちです。
ここの土塀は現存のものと復元のものが混じっています。
二の丸へ。いよいよ本日のメインである本丸・天守閣が見えてきます。
ここで腹ごしらえ。城まちステーションで買ったお弁当を広げて二の丸広場で食す。
天気も良く、とても気持ちが良いです。
本丸南御門をくぐって城内へ。
本丸の碑にはなんと猫が!
こちらは備中松山城の猫城主・さんじゅーろーです。
平成30年豪雨のときに保護された猫で、名前の由来は新選組の谷三十郎(備中松山藩士)だそうです。
真田丸に出てくる矢沢三十郎頼幸が由来かと思いましたが、違いましたね。。
ぼってりしていてとてもかわいいです。
管理人妻はお城よりも猫に夢中になっていました。
天守閣内部。現存天守にも関わらず写真撮影OKという太っ腹です。
城内には珍しい囲炉裏です。
暖を取るためのものでしたが、当時から城は火気厳禁のため、使われることは稀だったようです。
籠城のときに城主一家が入る「装束の間」です。
忍者も入れないように工夫がしてあるほか、落城時に自害をするための場所でもありました。
水谷氏の時代に作られた「御社壇」です。
修築を記念して作られた天照大御神を祀る祭壇です。
天守には地階がありますが、八の平櫓との間を繋ぐ渡り廊下になっていました。
天守閣の外に戻ります。ちなみに右側部分が八の平櫓跡で当時は天守閣との間で渡り廊下が繋がっていました。
天守閣の石垣も天然の岩盤と融合しています。野趣あふれた作りです。
本丸東御門です。本丸の勝手口になっていた部分です。復元です。
腕木御門です。本丸の裏門にあたり、ここから下りると搦手門に出ることができます。これも復元です。
天守と同様現存の二重櫓。北門は後曲輪、南門は天守に通じています。
気付いたら管理人妻が付いてきていませんでしたが、引き続き本丸広場でさんじゅーろーと戯れていたようです。昼に近くなって松山城が混雑してきている中で、管理人妻がさんじゅーろーを独占して撮った動画がコチラです。
こちらも真田丸のオープニングで使われていました。ほぼそのまま使われていたようです。
搦手曲輪から見上げる二重櫓です。
左側の階段は腕木御門に通じています。
元来た道を戻って駐車場へ。
なかなか見応えのある城でした。これにて散策終了です!
余談ですが、備中松山城に来ようと思って、間違えて「備中高松城」に行ってしまう人が結構いるみたいです。松山城登城の翌日、備中高松城に行きましたが、高松城の資料館でスタッフに「天守どこにあるの?」って聞いている方が二人ぐらいいました・・・
■公式パンフレット
コチラにも登城絵図がアップされています。
- 城名 備中松山城(高梁城)<日本百名城No.68>
- 種別 山城
- 登城日 2019年3月9日(土)
- 住所 高梁市内山下1
- 電話番号 0866-22-1487(備中松山城管理事務所)
- スタンプ設置場所 備中松山城券売所
- 公式HP 高梁市観光ガイド
- 入場料 無料
- 駐車場 有料・大人300円
- 所要時間の目安 180分程度
- 混雑度 中~大
- 注意点 特に無し
~城として~
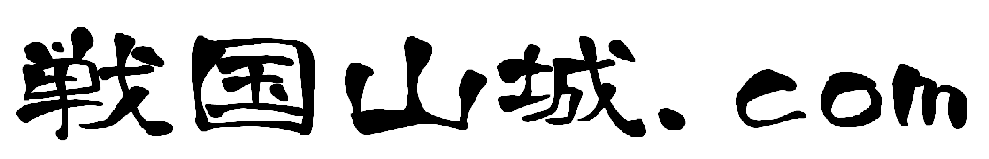











































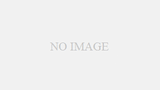
コメント