
■概要
江戸時代に、毛利氏をはじめとする西国の外様大名への抑えとして築かれた城です。
戦国時代、中国地方はすべからく毛利氏の支配下にありましたが、関ヶ原の戦いで西軍の総大将となったことで毛利氏は周防・長門二ヶ国に減封となり、備後国は東軍の先鋒として活躍した福島正則に与えられました。しかし、その後福島正則は武家諸法度違反により改易となり、代わりに徳川家康の従兄弟にあたる水野勝成が入封しました。
それまで備後国の政庁は、山城である神辺城にありましたが、過去に何度も落城している神辺城は西国大名への抑えとしては不十分であったため、勝成は異例の一国一城令発布下での築城を幕府に願い出て許可されます。しかも幕府からは、金12000両が貸与されるなど、ほぼ天下普請(幕府直轄事業)に近い位置づけでした。水害の多い低湿地での築城は困難を極めますが、廃城となった領内の神辺城はもとより、京都の伏見城からも建物が移築され、築城から3年の月日を要して元和8年(1622年)、ついに福山城は完成を迎えます。
その後勝成の死後も、福山城は「西国の鎮衛」としてその構造を維持し、水野氏の無嗣断絶後は欧州から松平氏、続いて阿部氏が入城します。その後、王政復古により長州の新政府軍が徳川譜代の福山藩を朝敵と見なして侵攻しますが、城主であった阿部正方が直前に死亡していたことから福山城はあっけなく陥落し、その後明治の廃城令により廃城となります。
廃城令後も、天守など重要な建物は残されましたが、太平洋戦争での米軍の空襲により焼失し、終戦後に復元されることとなります。
■見どころ
「西国の鎮衛」として、福山藩の規模としてはとても大規模な城となっています。
特に伏見城から移築された「筋鉄御門(すじがねごもん)」「伏見櫓」等は豊臣時代の古式な作りのものとなっており、必見です。江戸時代に作られた城ですので、戦国ファンとしては、伏見城の遺構として見るべきなのかもしれません。(実際の伏見城が模擬天守なので・・・)
■写真&散策記
ふくやま美術館前の駐車場に車を停めて散策開始です。
西御門の方から二の丸を通って天守にアプローチするイメージです。
遠くからも天守の姿を拝むことが出来ます。
大規模な桝形虎口になっています。
何か解説があってもよさそうなものですが、特に見当たりませんでした。
(見つけられなかっただけかもしれませんが・・・)
いよいよ天守閣が見えてきます。
虎口といい、天守といい、大大名にも遜色のない規模です。
こちらは鐘櫓。時刻を告げる鐘の他、緊急時に城下の武士を招集する太鼓も備えられていました。
こちらは本丸の正門にあたる筋鉄御門です。こちらも伏見櫓とともに伏見城から移築されました。
柱や扉に数十本の筋鉄が使われているためこのような名称が付けられました。
入母屋造りの初期様式のものです。
すぐ近くにJR福山駅が迫っています。
JR福山駅は山陽新幹線の駅ですが、これほど新幹線駅からアクセスの良い百名城は他にないかもしれません。
こちらも伏見城から移築されたことから伏見櫓と呼ばれる古式な望楼型の櫓で、伏見城松の丸東櫓が移築されたものです。
伏見西殿跡。本丸御殿が建っていた場所です。筋金門跡から入ったあたりにあります。
本丸広場に何やら風流な庭園がありますが、解説がないので詳細不明。
こちらも伏見城から移築した御湯殿です。戦災で焼失したため、現在の建物は復元です。
月見櫓も伏見城からの移築ですが、天守とともに復元されたものです。
本来は着見櫓と呼ばれ、当時は大手門も入江方面も展望できる南東隅に置かれていました。
現在は貸会場になっております。
こちらは鏡櫓です。明治の廃城令で取り壊されましたが、復元されました。
現在は福山城博物館(天守閣内)の文書館となっています。
最上階からはJR福山駅と市街地が一望できます。
当時は城の南側には海が迫っており、入り江となっていました。
現在の天守裏手に復元前の旧天守の礎石が移築されていて、現天守の最上階から見下ろすことが出来ます。
東への下り口は虎口のようになってますが、特に遺構ではなさそうです。
全体的に解説少なめなので、このあたりが何にあたるのか良く分かりません。
築城主である江戸幕府譜代・水野勝成の像です。
お城の東側からひっそりと福山城を見守っています。
- 城名 福山城(久松城)<日本百名城No.71>
- 種別 平山城
- 登城日 2019年3月9日(土)
- 住所 広島県福山市丸之内1-8
- 電話番号 084-922-2117(福山城博物館)
- スタンプ設置場所 福山城天守閣内
- 公式HP 福山城博物館公式HP
- 入場料 無料
- 駐車場 有料・150円/30分
- 所要時間の目安 60分程度
- 混雑度 小~中
- 注意点 特に無し
~城として~
- 難攻不落度 ★★☆☆☆(あまり見受けられません)
- 歴史に浸れる度 ★☆☆☆☆(江戸時代に入ってからの城なので・・・)
- 他では見れない度 ★★☆☆☆(伏見城の遺構として見るべきかもしれません)
- 総合評価 ★★☆☆☆
- アクセス性 ★★★★☆(JR新幹線福山駅から徒歩1分です)
- 登城のしやすさ度 ★★★★☆(とても回りやすいです)
- 分かりやすさ度 ★★★☆☆(もう少し解説が多くても良いかもしれません)
- 景観度 ★☆☆☆☆(眺望は期待できません)
- 女性と行ける度 ★★☆☆☆(厳しいかと思います)
- 総合評価 ★★★☆☆

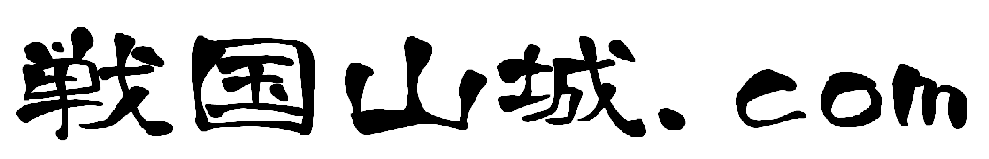






















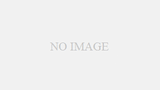
コメント